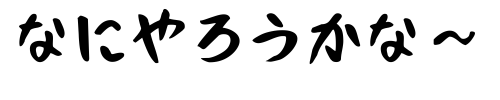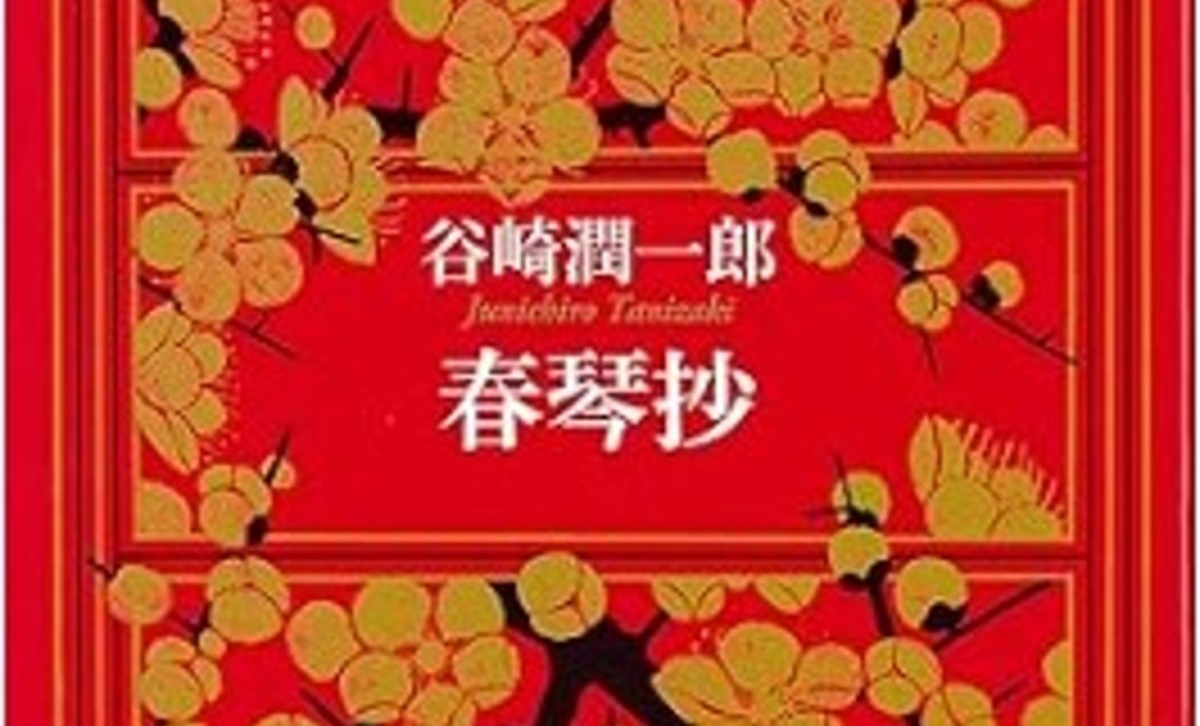若い頃は、純文学・歴史文学なども多少は読んだが、26歳を過ぎてコンピュータの世界に入ってからは圧倒的にコンピュータ雑誌、専門書だった。
大学では化学出身だったので電気、ソフトの知識はほぼゼロ。
会社に入ってからはハードウェア設計をやっていたのでFPGA設計法、電気回路図を書いていたのでCADの使い方の本、ファームも組んでいたのでC言語、40過ぎからはハードウェアの仕事が無くなってパソコンソフト設計に転向してC++言語などをやってきたが、全て本を購入しての独学。
色々覚えたつもりだが、ブログで技術を提供するほどの知識は無い。
70歳を過ぎて完全には引退していないが、時間が相当取れるようになったので、一般文学の読書を
するようにした。
何を読もうと色々考えたが、図書館に行って色々閲覧してこれだと決めた。
新潮日本文学アルバム全75巻。
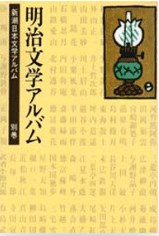


誰の本を読もうというより、誰がいるのか、どんな経歴を踏んできたのか、その辺を理解してから
作家を決めて読んでいくことにした。2022年5月から読み始めて9月一杯かかった。
色々読みたい作家は多々あったが、やはり最初は夏目漱石の坊ちゃんから入った。
それから芥川龍之介、太宰治、谷崎潤一郎、永井荷風、・・・・
谷崎潤一郎、永井荷風などはそれまでも読んだことは無かったが、谷崎潤一郎の春琴抄などは
一風変わった内容で、自分はとても佐助のような世界には入れない。
坊ちゃん以降、夏目漱石の本を読んでいったが中身がよく分からない。
前期三部作、後期三部作を続けて読んでいったが、どのように理解していったらいいのか
なかなか分からなかったが、インンターネットで概要を確認してから読んでいくと分かってきた。
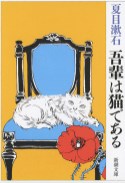
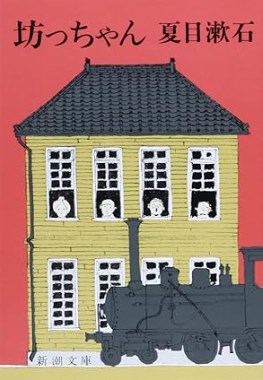
それから3年たった現在(2025年7月)、文学の読書の習慣は続けているがペースは遅くなっている。健康に関する本が増えて来た。体にガタが来ているので自然とそういう方向に向くのは仕方のないことと割り切っている。
まず多いのは”アルツハイマーの身内を抱えて”、”ガンを乗り越えた”、”うつ病との闘い”、”透析の世界はつらい”、”糖尿病にならないためには”等々の病気を抱えた本人、それを支えた身内の気持ちを書いた本、
また”死後の世界”、”死は怖くない”等々の死後の世界に関する本。

健康を維持するために運動療法、食事療法を考えているが腰痛が酷いため食事療法を中心に考えている。最近であるが。
この辺のことは、ここに書いているので関心があれば見てください。
また、最近医療器具にも関心を寄せている。
体組成計は以前から持っているがスマホ連携体組成計に買い替える予定。
血圧計(手首)も相当前から使っているが、最近壊れたので同じメーカの機能アップ版を購入した。
この辺はどなたでも持っていると思うが、今後購入したい機器は以下の3点
・血中酸素濃度計(睡眠中も図れるもの。睡眠時無呼吸症候群の可能性があるので)
・血糖値測定器(購入予定はFreeStyleリブレ。これはいい!)
・診療テーブル(整体に行ったら、そのテーブルの上で行ってもらうやつ。嫁さんと二人で交互に
マッサージを行う時に床だと疲れるので。)
読書の話題とは、だんだん内容が離れてきてしまった。
最近、有名人で亡くなる方が自分と同年代に近い人が多くなっているので健康対策の方が優先になって
しまう。
今後も並行して読書は続けていく。
感想文なども含めてカテゴリ”読書”に投稿していこうと思う。
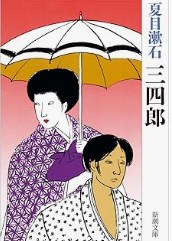
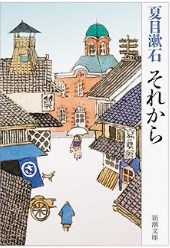
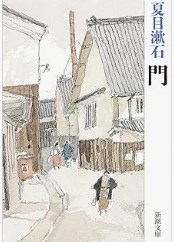
昔からそうであるが、文学系の本は幕末、戦国時代、徳川十五代、新選組辺り、純文学と言えば明治、大正文学から抜け出せない。
夏目漱石、芥川龍之介、太宰治、石川啄木等々の有名どころの本を読み返している。
あまり人数は多くなかったが、最初にも書いたが 新潮日本文学アルバム全75巻 を読み終えてから
色々な作家の生き様を知り、今まで読んだことのない作家の本も読むようになった。
谷崎潤一郎、永井荷風、有島武郎等々
人数が多いので読んでも1,2冊しか読めない。
最近は夏目漱石を集中的に読んでいる。最初は 吾輩は猫である を読み始めたが長編過ぎて1/3
くらいで断念した。筋は分かっているつもりであるが、なかなかのめり込めない。
次に 坊ちゃん を読む。分かりやすい。
続いて前期三部作、後期三部作と読み進めていった。が又分からなくなってきた。熊本から出て来た
三四郎が中心なのはわかるが、単なるほのかな恋愛小説として読んでいたがインターネットであらすじを読んでから以後の本の見方が替わった。人間の恋愛感情、葛藤、疑心等々を描いた作品だということ。そういった気持ちを持って読んで行けば、次第にスムーズに読めた。
2025年7月21日 記
夏目漱石 行人 を読み終えた。疲れた。こういった高学歴でかつ先生をやっている人の感情。
明治時代だから、こういった心情の人もいたかもしれないが特殊な部類の入る人であろう。
今どきはこんな感情を持って結婚生活をしている人なんていないと思う。
2025年7月30日 記
こころ すんなり読めた。何か漱石のこの時期の文学は明治時代後半の時代状況なのかもしれないが
暗い。こころ は高校の教科書にも載っているそうだが、なかなかこの頃の先生の心情を理解するのは
難しいのでは。読んでいて友人を自分のアパートを紹介する状況になった時、下宿屋のお母さんが言った よした方がいいのでは と言ったのは、先々の恋愛のこじれを見抜いていたのだと思う。
自分ならお嬢さんを気に入ってたのなら絶対に紹介しない。
やはり競争相手になる可能性があるので。
こういうことを考えながら読むと疲れる。
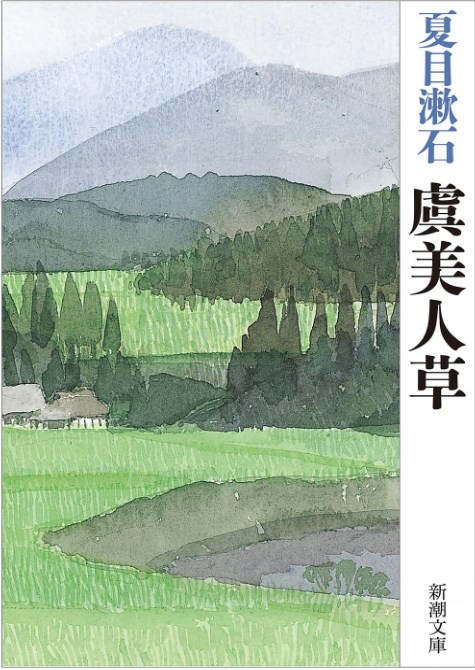
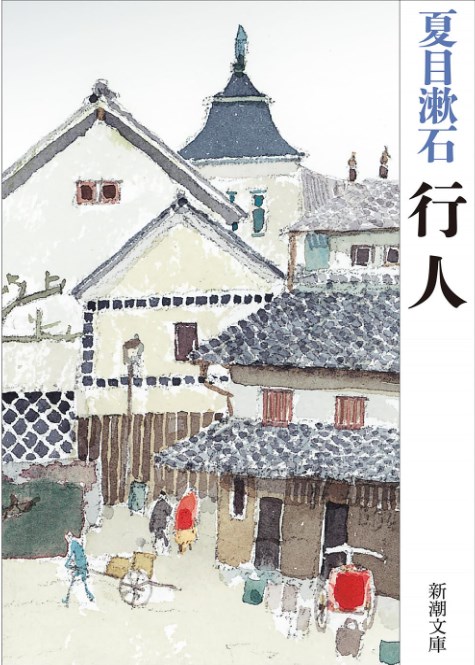
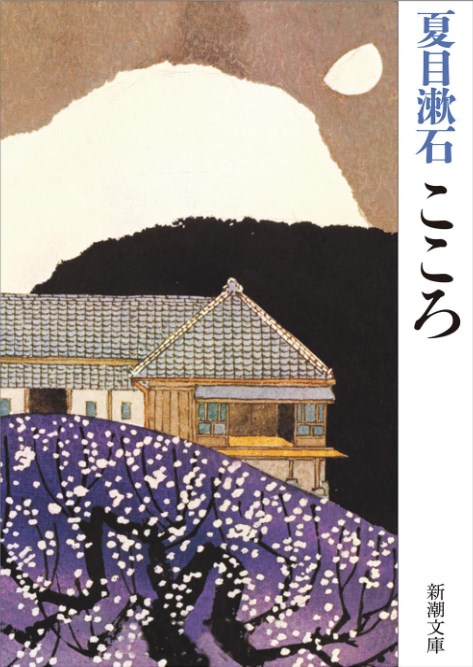
次は 虞美人草 を読む。
2025年8月15日(金)
2週間かかって読み終えた。前回は途中で断念したが、今回は読み終えることが出来た。
以前も書いたが、漱石の本は前半1/3を過ぎないと佳境に入ってこないので読み通すことが
難しい。かつ予めインターネットであらすじを知っておくこと。
私だけかもしれれないが。50%を読み終えると2~3日で読み終えた。
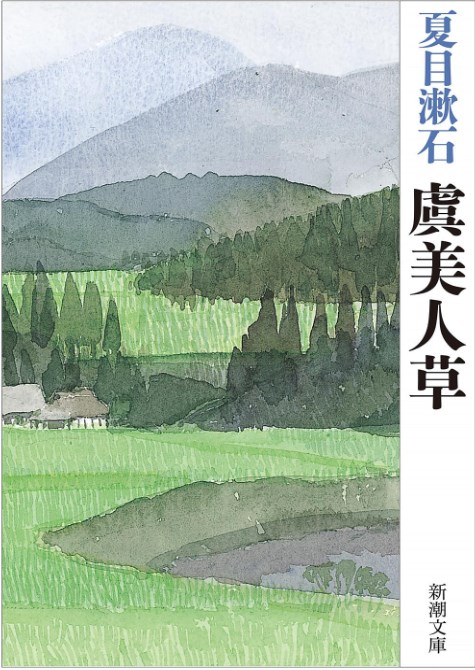

やはり、宗近、小野、甲野、藤尾、糸子、小夜子らの恋愛関係の情景が具体的に書かれている段になると読書スピードが俄然速くなった。それまでの文章はなかなか文章を読むだけで難しく惰性で読んでいる感じだ。いちいち文章をゆっくり読んで一文一文を理解しながら読む気にはなれない。